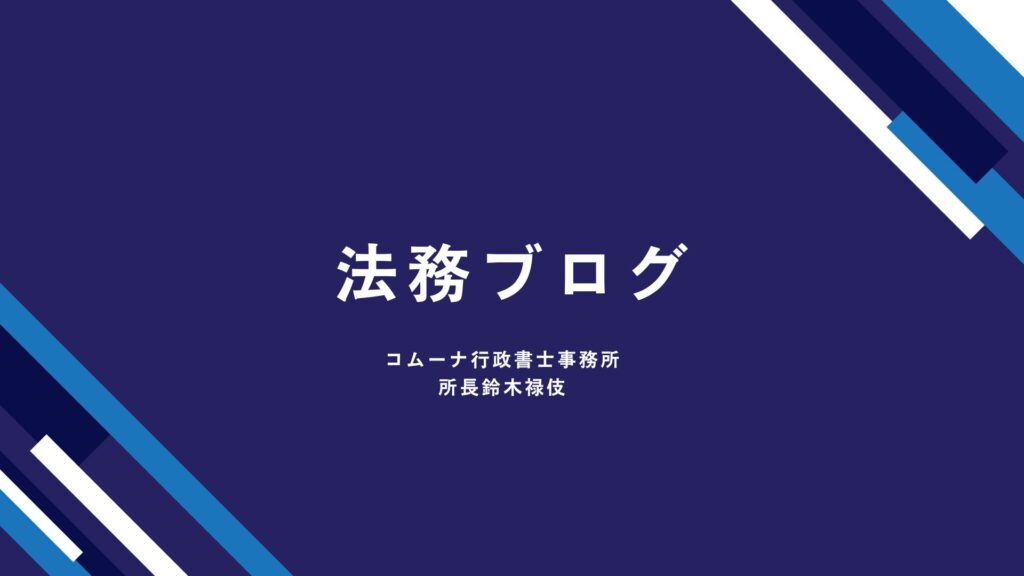
「特定技能外国人の受入計画書って何?」
「どんなことをしなければいけないの?」
「建設業で外国人材を扱う際には、どんな制約があるのだろう?」
日本の人材不足の中で、特に建設業はそれが目立っています。
外国人を雇いたい、という方もいるかもしれません。
実は建設業界で特定技能を雇うのは、結構様々なプロセスと制約を受けます。
今回はそのひとつである「受入計画書」について書いていきます。
建設業における特定技能受入計画とは?
それは、建設業界に日本人があまり入りたがらないこととも関連しています。
建設業は、ハードな職業として知られ、また古風な上下関係もあります。
それゆえに、外国人材の定着が難しく、そうなると特定技能制度の意義が揺らいでしまうため(要するに単なる国際間の労働力搾取にならないようにするため)、
特定技能を受け入れる際には建設業特有の規制やプロセスがあります。
特定技能受入計画とは、要するに、「ちゃんと適正な計画を立てていますよ」ということを伝えるものとなります。
主な記載内容
受入計画には以下のような内容を記載します。
| 項目 | 内容の例 |
|---|---|
| 就労場所・業務内容 | 配属先、職種、日々の作業内容など |
| 労働条件 | 賃金、労働時間、休日、福利厚生 |
| 生活支援体制 | 住居の確保、生活オリエンテーション、日本語学習支援など |
| 教育・研修 | 安全衛生教育、技術研修の内容と実施方法 |
| 相談・苦情対応 | 支援責任者・相談窓口の設置について |
| 離職時の対応 | 離職後の転職支援や支援継続の方針など |
提出先と役割
建設業では、国土交通省(地方整備局等)に対して提出します.
審査を経て適正と認定されると、入管での在留資格手続きに進むことができます。
なぜ必要なのか?
特定技能制度では、外国人が「単なる労働力」として扱われないよう、
日本人と同等の待遇、適切な支援が求められています。
このため、「受入計画」を通じて以下のような確認がされます。
- 不当な労働条件ではないか?
- 生活支援や相談体制が整っているか?
- 就労先に技能を活かせる環境があるか?
つまり、受入計画は単なる手続き書類ではなく、外国人材の健全な受け入れと、企業の社会的責任を果たすための土台となる計画なのです。
そして国際間の関係を担保するための制度となっているわけです。
特定技能受入計画の流れと必要書類
特定技能制度は、即戦力となる外国人を受け入れるために2019年から始まった制度です。
建設業も対象業種に含まれており、慢性的な人手不足の解消に役立っています。
ただし建設業は実は、人間関係も労働もいわゆるキツく、外国人の失踪が多い分野となってしまっているのが現状です。
ですから受け入れには「受入計画」の策定と申請が必要であり、制度の仕組みや提出書類についての理解が必要です。
この記事では、受入計画申請の流れや必要書類、申請時の注意点に加えて、申請書作成のコツや建設業特有のルールについても解説します。
受入計画申請の流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1. 外国人の選定 | 特定技能評価試験・日本語能力試験の合格が必要。 |
| 2. 受入計画の作成 | 就労内容、支援体制、教育方針などを計画書にまとめる。 |
| 3. CCUS登録 | 建設キャリアアップシステムに企業・外国人ともに登録。 |
| 4. 国交省への申請 | 地方整備局等へ「受入計画」を提出し、審査を受ける。 |
| 5. 在留資格の申請 | 入管へ在留資格の申請を行う(計画認定申請と同時並行可)。 |
| 6. 就労開始 | 許可後、就労スタート。支援体制の実施・報告が必要。 |
必要書類一覧
必要書類を確認していきましょう。
- 建設特定技能受入計画(新規申請) ⇒ こちらはオンラインで入力です
- 登記事項証明書、住民票(原本)等
- 建設業許可証の写し
- 常勤職員数を明らかにする文書
- 建設キャリアアップシステムの事業者IDを確認する書類
- JACの会員証又はJACの正会員である建設業者団体の会員であることを証する書類
- 弁護士証票又は行政書士証票(代理申請を行う場合のみ)
- ハローワークで求人した際の求人票
- 同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
- 就業規則および賃金規程
- 同等の技能を有する日本人の賃金台帳
- 同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類
- 特定技能雇用契約書および雇用条件書
- 時間外労働・休日労働に関する協定届、変形労働時間に係る協定書、協定届、年間カレンダー
- 雇用契約に係る重要事項事前説明書の写し
- 建設キャリアアップシステムカードの写し
こうしてみていると、そもそも特定技能受入計画の認定申請をする以前に、以下の行為が必要となることがわかります。
- 建設業許可の取得
- 建設業キャリアアップシステム(CCUS)への登録
- ハローワークでの該当業種への求人
他のことは会社内で整備できるかもしれませんが、これらは客観的な行動がなければなりません。
ちなみに建設業許可の取得、CCUSの登録も、行政書士の業務範囲です。
受入計画申請書作成のポイント
受入計画書の作成では、以下の点を意識することでスムーズな申請が可能になります。
支援内容は具体的に
単に「日本語教育を行う」と記載するだけでなく、「週1回、社内の日本語講師が実施」「業務マニュアルを母国語と日本語で提供」など、具体的な支援内容を記載することで審査も通りやすくなります。
これは登録支援機関と共に考えるとよりよくなるでしょう。
こちらも読みたい:特定技能における登録支援機関とは?
労働条件は日本人と同等以上に
賃金や福利厚生面で日本人との均等待遇が求められます。
最低賃金を下回っていないか、同職種とのバランスが取れているかを確認しましょう。
特定技能を雇う際には日本人にはない費用が発生します(JAC、登録支援機関サポート料金等)。
そうなってくると、同一賃金だと割高に感じる事業者もいるかもしれませんが、
それらを理由に賃金を引き下げることは認められません。
教育体制も明記
建設分野では安全衛生教育も重要です。
職長教育や安全講習の実施計画も盛り込むと好印象です。
特定技能における建設分野特有の注意点
建設業での特定技能外国人の受入れには、他分野にはない独自の要件があります。以下に主なものをまとめます。
対象職種(特定技能1号)
建設業で特定技能の対象となる職種は以下のとおりです。
| 区分 | 対象職種例 |
|---|---|
| 土木 | とび、型枠施工、鉄筋施工、舗装、土工など |
| 建築 | 左官、内装仕上げ、建築大工、屋根ふき、など |
| ライフライン・設備 | 配管、電気通信、建築板金、保温保冷 |
受入人数制限あり
建設分野では、特定技能外交人の受け入れ可能な人数が制限されています。
以下のような基準がありますので、ぜひともご参考にしてください。
【1号特定技能外国人の数が、受入機関の常勤の職員(外国人技能実習生、1号特定技能外国人を除く)の総数を超えないこと】
常勤の職員とは社会保険に加入している職員のことを指します。
要するに、普通に働いている日本人(又は帰化した者や永住者等就労制限のない在留資格で滞在している者)の数を超えてはいけないですよ、ということになります。
特定技能外国人(建設業)は直接受入が原則
特定技能外国人を建設業で雇う際には、直接雇用されることが必要です。
派遣等の間接的な雇用は、認められていませんので十分注意していきましょう。
実はかなり大変な建設業界の特定技能受入
建設業における特定技能外国人の受入れは、人手不足対策としていいでしょう。
しかし、受入計画申請の手続きは煩雑で、建設業特有の要件にも注意が必要です。
- 支援体制の具体性
- 労働条件の明確化
- CCUS登録・受入制限などの遵守
以上を意識して、制度を適切に活用しましょう。
なおかつ支援に関しては多くの場合、登録支援機関に委託することになります。
そしてJACという機関にも所属し、入会金や月額を支払うことになります。
こちらも読みたい:建設業で特定技能を雇う際に必要なJACとは?
本当に「なんで、外国人を雇うだけなのに、こんなにお金がかかるんだ…」と最初は思うことかもしれません。
もし特定技能外国人の受入を考えているのなら、まずは計画を立てることから始めていきましょう。
もちろん、そちらもサポートしていきますよ。
詳しくはこちら:国土交通省 建設特定技能受入計画のオンライン申請について【新規】