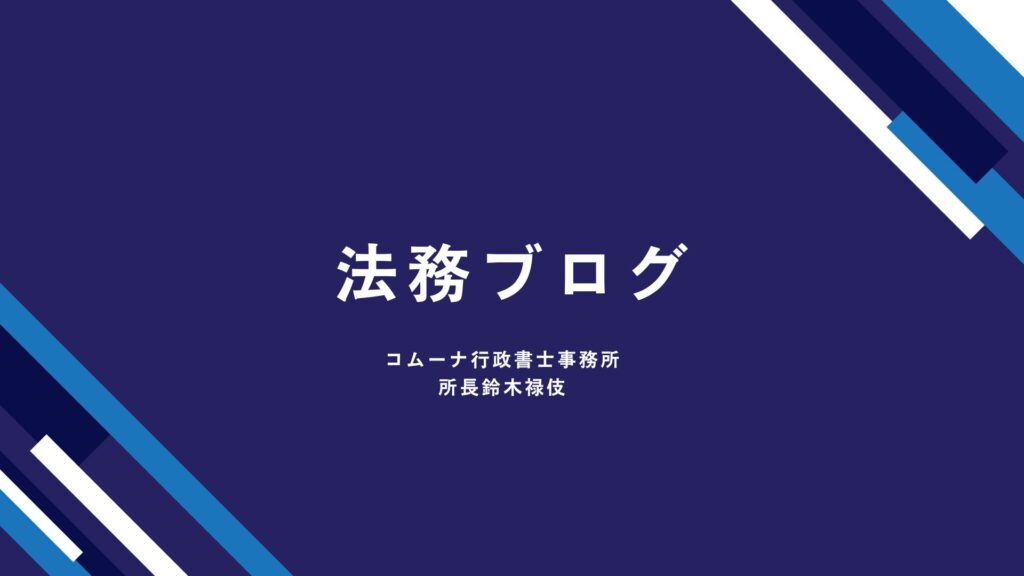
「外国人には労働法は適用される?」
「雇用における注意点は?」
「年金の扱いっていったいどうなるの?」
日本に来て働いてくれる外国人の数が増えてきています。
日本で労働人口が低下している分、これはますます増えていくでしょう。
しかし外国人の労働には外国人であるが故の独特の問題がつきまといます。
今回はそんな「外国人と労働法」という観点でコラムを書いていきます。
外国人にも労働法や健康保険は適用される
原則として外国人にも労働法の諸規制や健康保険や年金などの社会保険関連の制度は適用されます。
つまり日本人と同様の扱いをし(残業、休日、休憩時間、安全確保等)、そして外国人でも日本の年金を支払う必要があるということになります。
日本人の場合は稀に社会保険に入らない方もいますが、外国人だとそれが許されません。
差別的取り扱いは労働基準法3条で禁止
もちろんそれ以外の場面でも差別的な取り扱いは禁止されることになります。
労働法には以下のような記載があります。
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
労働基準法3条
外国人の差別的な取り扱いは、法律で禁止されていることになります。
社会保障の二重加入問題はどうするか?
またたとえば年金を日本で支払っても、外国人の本国では適用されずに意味がないといったことも起こり得ます。
こういった問題のことを「社会保障制度の二重加入問題」と言います。
(2国以上で同じような内容の社会保障制度に加入している状況を指します)
これに関しては、最終的に利用する社会保障制度が一つになるように調整を行い、他の国にいたときの期間はその制度に合算する、という措置がとられます。
つまり、日本で払った年金も母国での年金にすることができる、ということになります。
しかし、これは日本とその旨の協定を結んだ国のみが対象となります。
(具体的には現段階では、西欧諸国、ブラジルやインド、フィリピン等ということになります)
詳しくはこちら:日本年金機構 社会保障協定
外国人と労働上の手続き
実際に外国人と契約を交わすにあたって、
やはり労働関連法の規制が適用されるということで、必要な手続きがたくさん生まれます。
それを整理していきましょう。
労働条件の通知
実際に雇用契約締結の前に、労働条件の通知は必要になります。
その際に通知すべき内容は以下になります。
- 労働契約期間に関する事項
- 期間を更新する基準に関する事項
- 就業場所及び従事する業務
- 始業と終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
- 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇事由等)
- 退職手当に関する事項
- 臨時に支払われる賃金、賞与等及び最低賃金額に関する事項
- 労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰及び制裁に関する事項
- 休職に関する事項
こちらはメールなどで送ることも可能になります。
就業規則もチェックしておこう
常時10人以上を雇用している事業者は就業規則(上記条件をいつでも見れるようにしたようなもの)の作成が義務付けられます。
こちらも外国人を雇うことによって、微妙に内容を変える必要があったりします。
また、雇っている外国人にわかるように就業規則を周知しておいた方がいいです。
退職における注意点
外国人が会社をやめた際には、社会保障における脱退一時金を請求することができます。
ですから、退職時に脱退一時金の説明はしてあげるべきでしょう。
脱退一時金とは要するに「少ない期間だとしてもしっかり払った年金は請求すればもらえる」という制度になります。
こういった外国人特有の問題に対処できるようにマニュアルを作っておきましょう。
外国人材に必要な届出
外国人を雇う場合、日本人とはまた別に必要な届出がどうしても生まれてしまいます。
そちらもチェックしておきましょう。
外国人材にまつわる書類【図解】
| 書類 | 留意点 |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | 備考欄に「国籍・地域」や「在留資格」を記入する必要あり |
| 外国人雇用状況届出書 | 雇用保険の被保険者でない外国人の場合 |
| 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 特になし |
| 健康保険被扶養者届 | 被扶養配偶者がいる場合 |
| 国民年金第3号被保険者該当届 | 被扶養配偶者がいる場合 |
| ローマ字氏名届 | 在留カードに記載されているローマ字を年金事務局へ届ける |
こうしてみると、外国人であるからといってそれほど特別な手続きは要りませんね。
ところどころ注意をしてやっていけば大丈夫だと思います。
もちろん入管上の手続きも必要
実は過去、外国人の在留資格の管轄につき法務省と厚生労働省で争ったという過去があります。
最終的に法務省の管轄となりました。
ですから上のように主として厚生労働省管轄の手続きだけでなく、もちろん法務省管轄の手続き(つまりは入管上の在留資格関連の手続き)もしなければなりません。
こちらは他のコラムで書いていますのでここでは割愛しますが、以下の点は大切です。
外国人を雇うためには、①入管法の手続き ②労働・社会保険関連法上の手続き 双方を適正にこなし、かつ維持する必要がある、ということです。
特に労働関連法令に違反しても即アウトであり、今後外国人材を受け入れることが難しくなる、ということは注意です。
常に適正な運営が必要になるということだからです。
こちらも読みたい:ビザ申請、どれくらいで結果が出る?
外国人材と労働法における適正な運営のために
今回書いたことは必要な体制を構築するための、まだほんの一部の知識となります。
外国人雇用の責任は重い
ある種深刻に考えていただきたいのは、「外国人を雇う際には今まで以上に責任が生まれる」ということです。
責任とは具体的に、労働・社会保険関連の法律の遵守とういうことになります。
コンプライアンスが今まで以上に求められ、なおかつ行政の監視も厳しくなります。
なぜなら、来てくれた外国人に何かあった場合、国際問題に発展し、日本の信頼が揺らいでしまうからです。
考えてみてください。
「日本人が他国で労働力として明らかに都合よく使われていたらどう思いますか?」
そのために法務省も厚生労働省も全力で外国人労働のコンプライアンス徹底に尽力しています。
こちらも読みたい:特定技能って単純労働の解放?
雇用する事業者の総合的なサポートをいたします
事業者側も、安易な考えではなく、その背景をくみ取って真摯に向き合っていきたいですね。
もし、何かわからないことがあれば、弊所にご連絡くださればと思います。